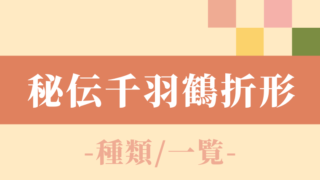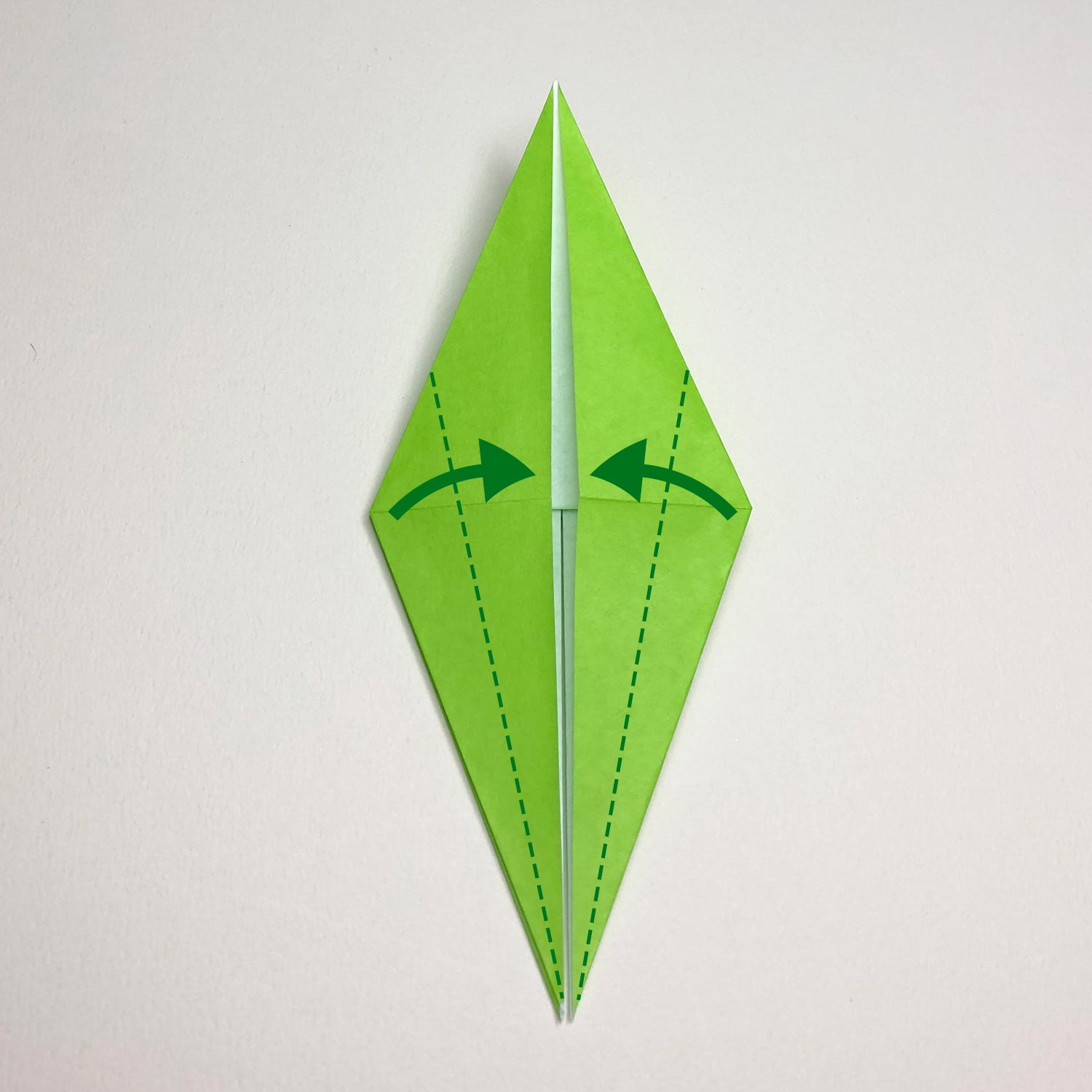
(39)
両側を矢印の方向に動かし、折り目をつけていきますが、
こちらは、中心の線にしっかり合わせずに、
少しすき間を空けて折りましょう。

(40)
写真のように、中心の線から少しすき間を空けて折ります。

(41)
全体の写真がこちらです。
すき間を空けておくと、後の手順で折りたたみやすくなります。
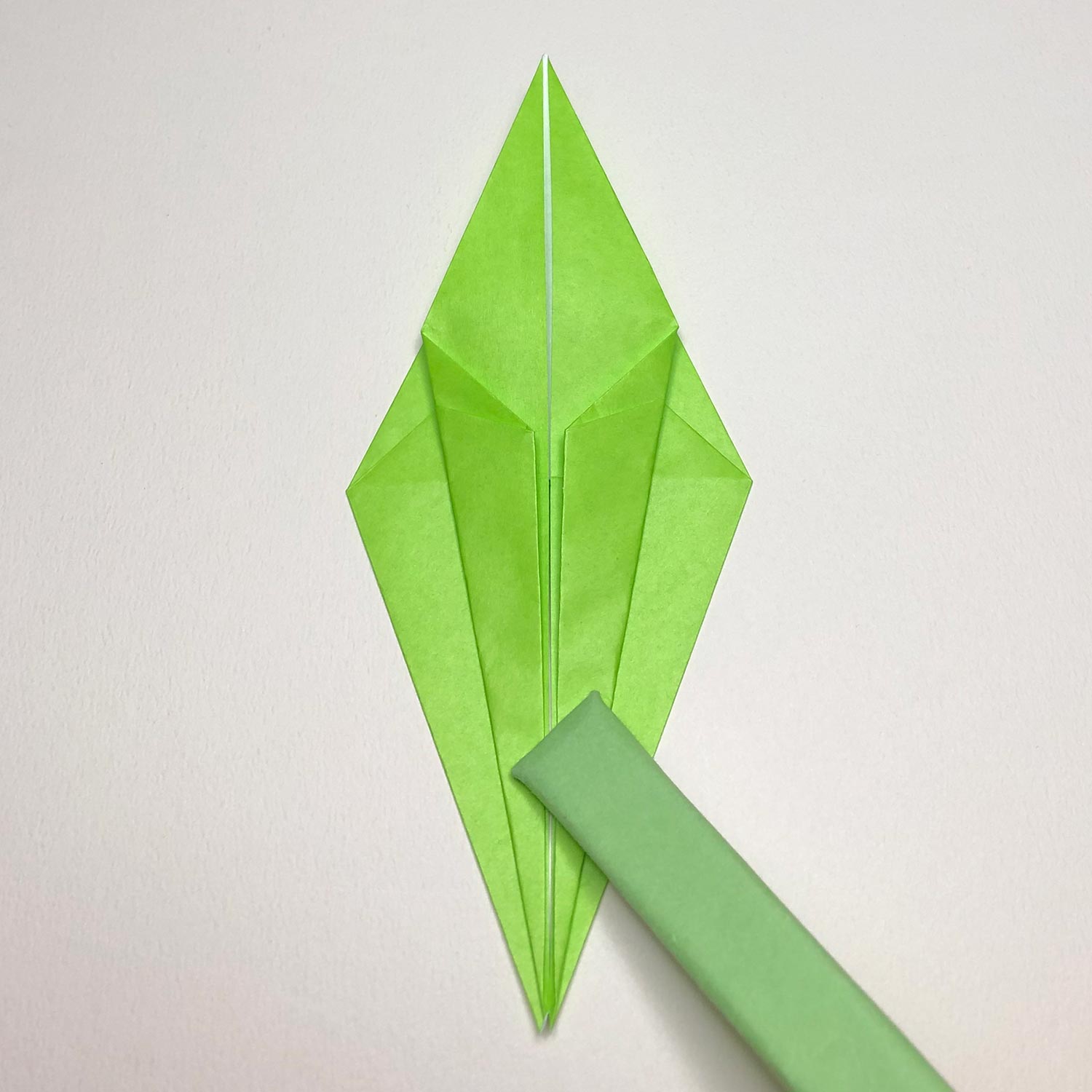
(42)
折り目をつけたら、そのまま裏返しましょう。
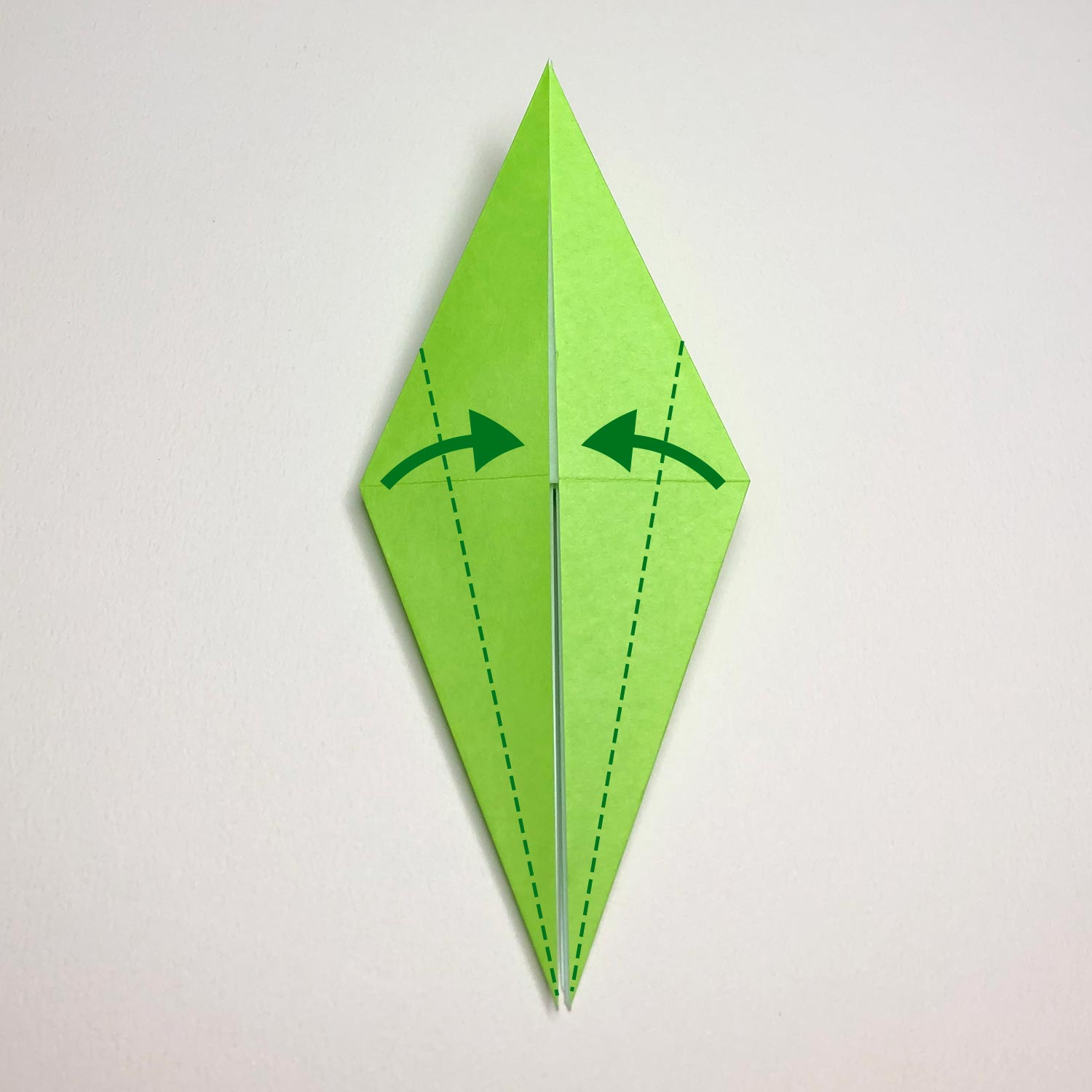
(43)
紙を裏返したら、
両側を矢印の方向に動かし、折り目をつけていきます。

(44)
折り目をつけるとこのようになります。
こちらも、少しすき間を空けておきましょう。

(45)
続いて、片側を矢印の方向に少し開きます。
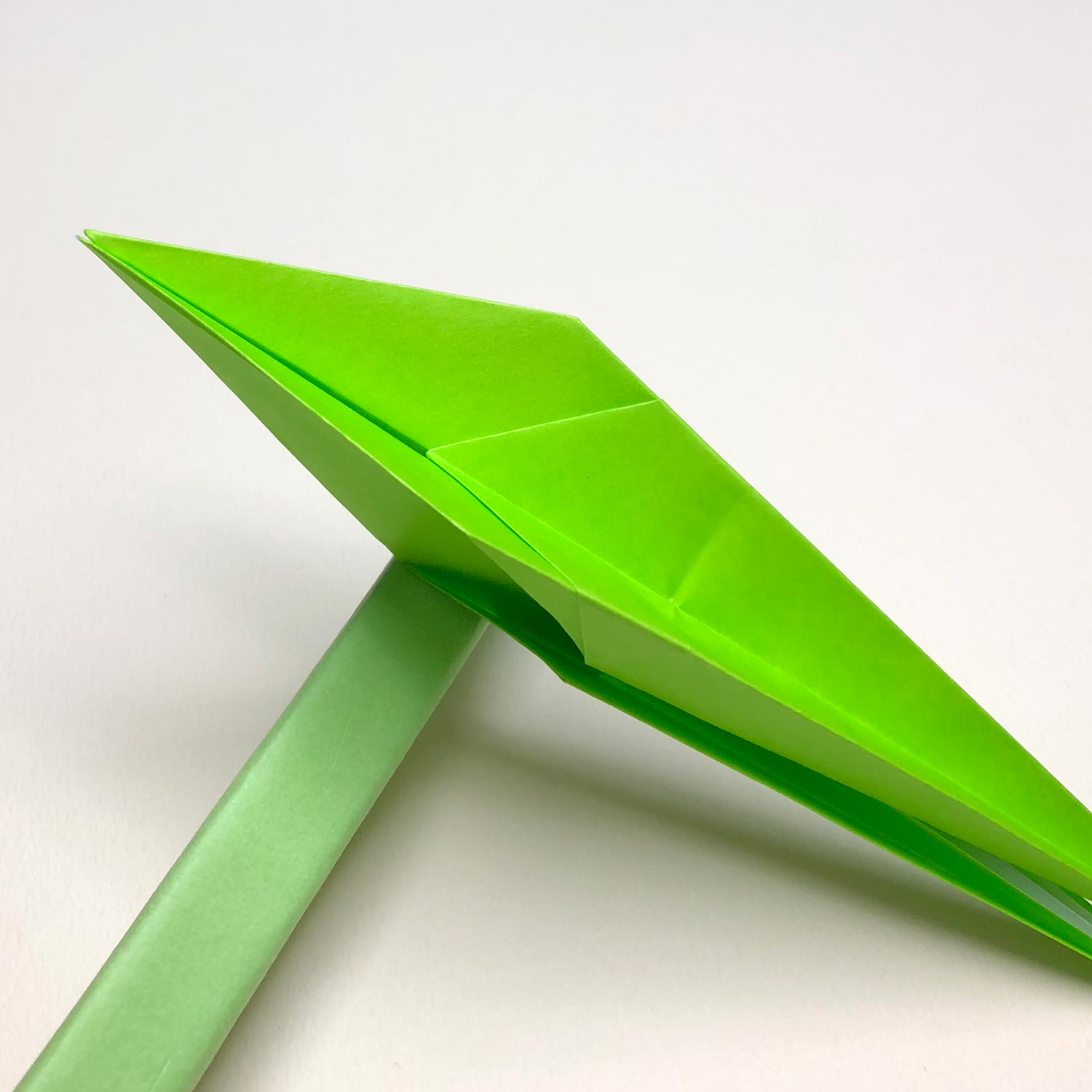
(46)
このように開きましょう。

(47)
下側を矢印の方向に動かし、
すでに折り目があるところ(点線部分)で折りたたみます。

(48)
このように折りたたみます。
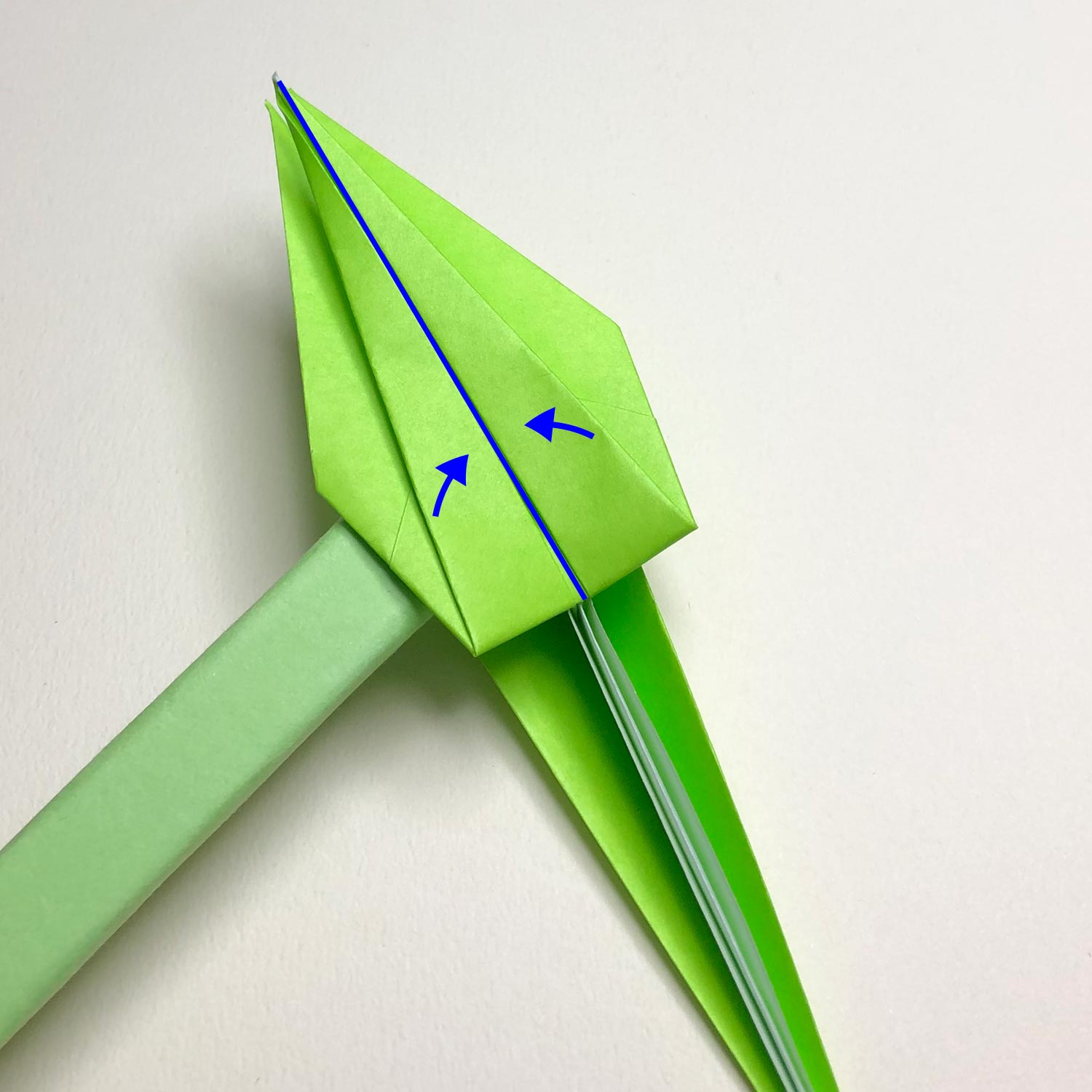
(49)
両側を矢印の方向に動かし、
青い線のところに、軽く折り目をつけましょう。

(50)
このように折り目をつけます。

(51)
(39)と(43)番目の手順で、少しすき間を空けて折ることで、
青い丸のところにすき間ができ、折りたたみやすくなります。
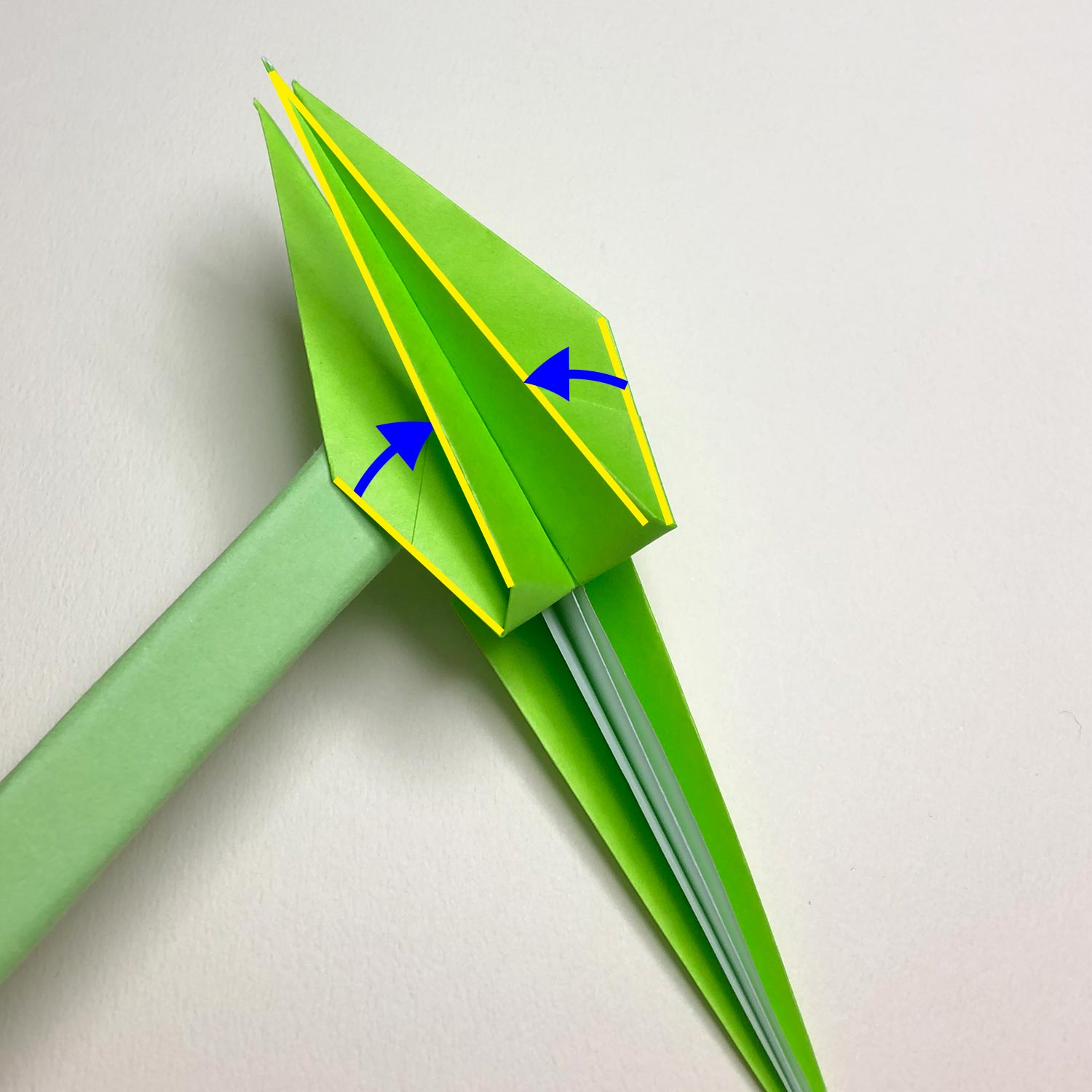
(52)
外側を矢印の方向に動かし、
黄色い線のところをそれぞれ合わせていきます。
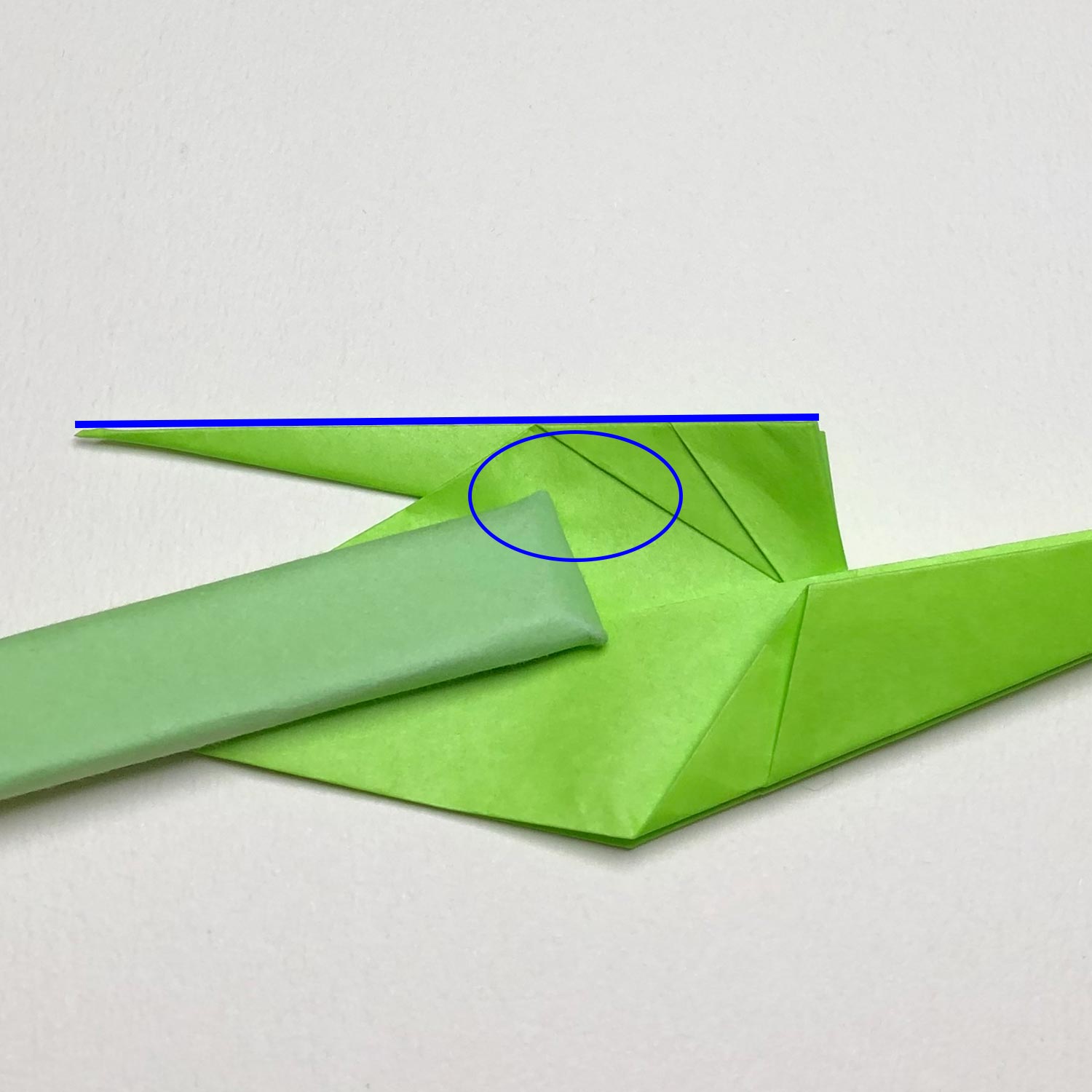
(53)
青い線のところが、平らになるように合わせましょう。
平らになるように合わせたら、
青い丸のところを両側からつまみ、紙を抑えます。
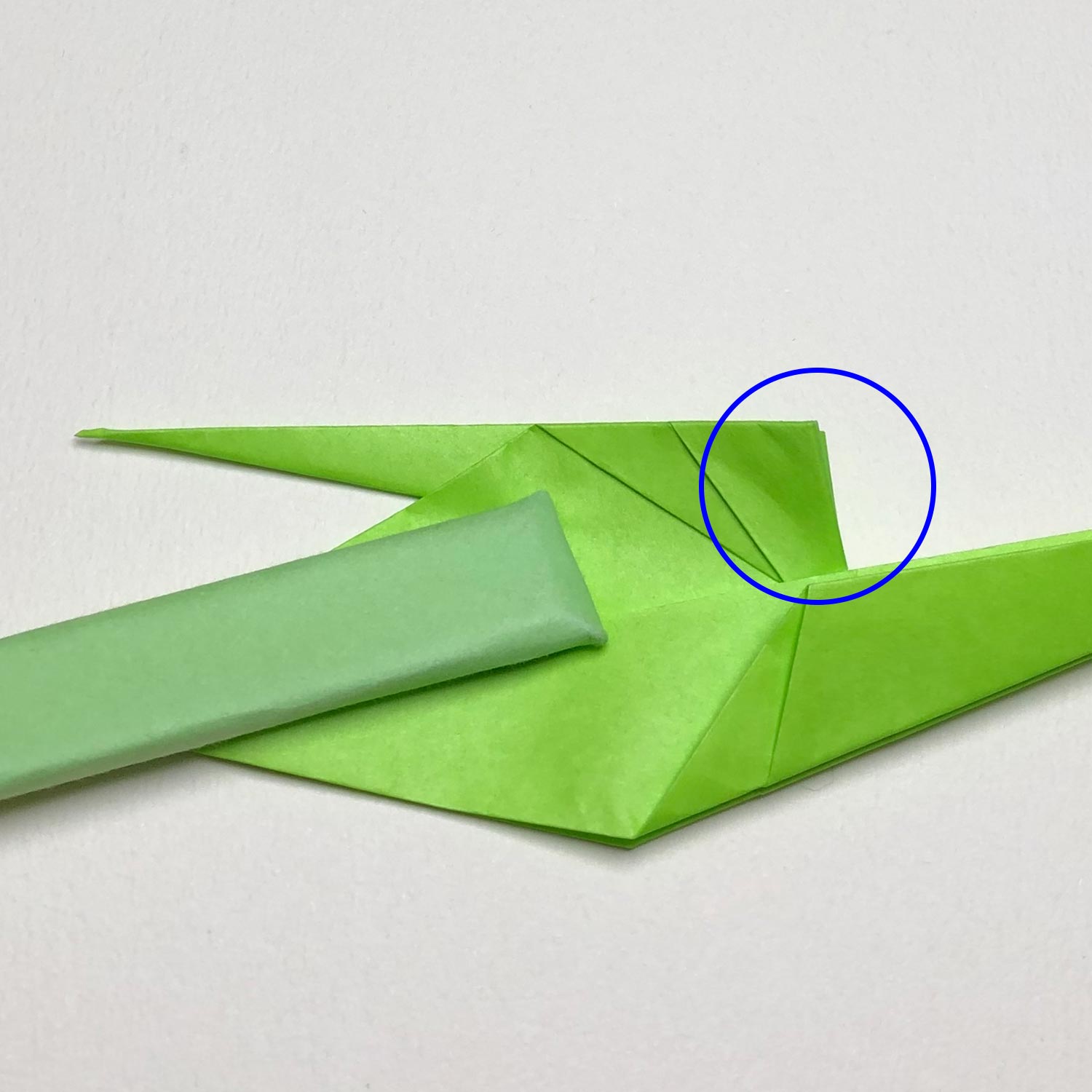
(54)
紙を抑えながら、
青い丸のところに折り目をつけましょう。

(55)
折り目をつけるとこのようになります。

(56)
横から見るとこのようになります。

(57)
折り目をつけるときに、
青い丸のところが、写真のような形になり、
折り目がつけづらくなる時があります。

(58)
その場合は、矢印の方向から、爪で軽く押すと、
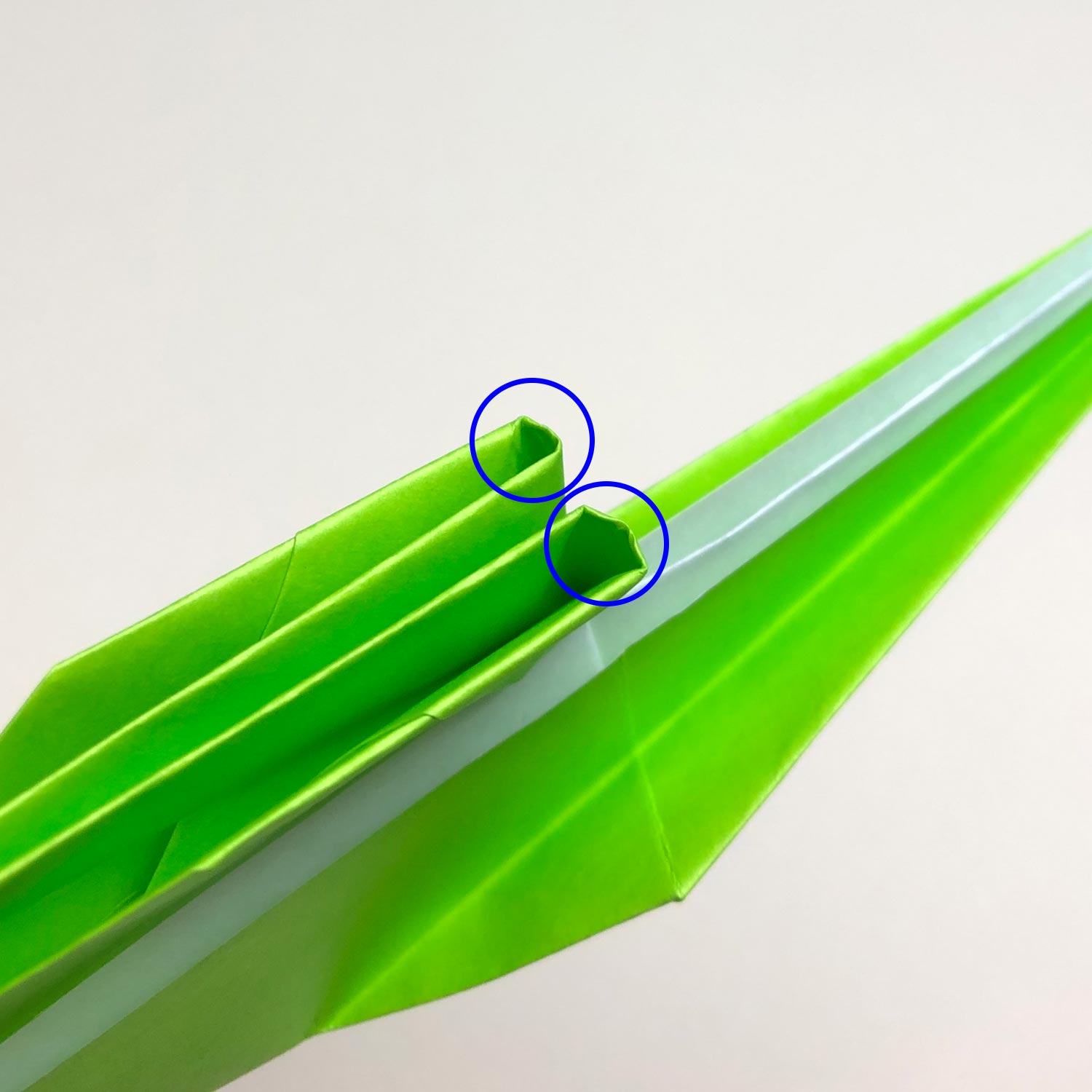
(59)
写真のように、少し丸くなるので、
折り目をつけやすくなります。
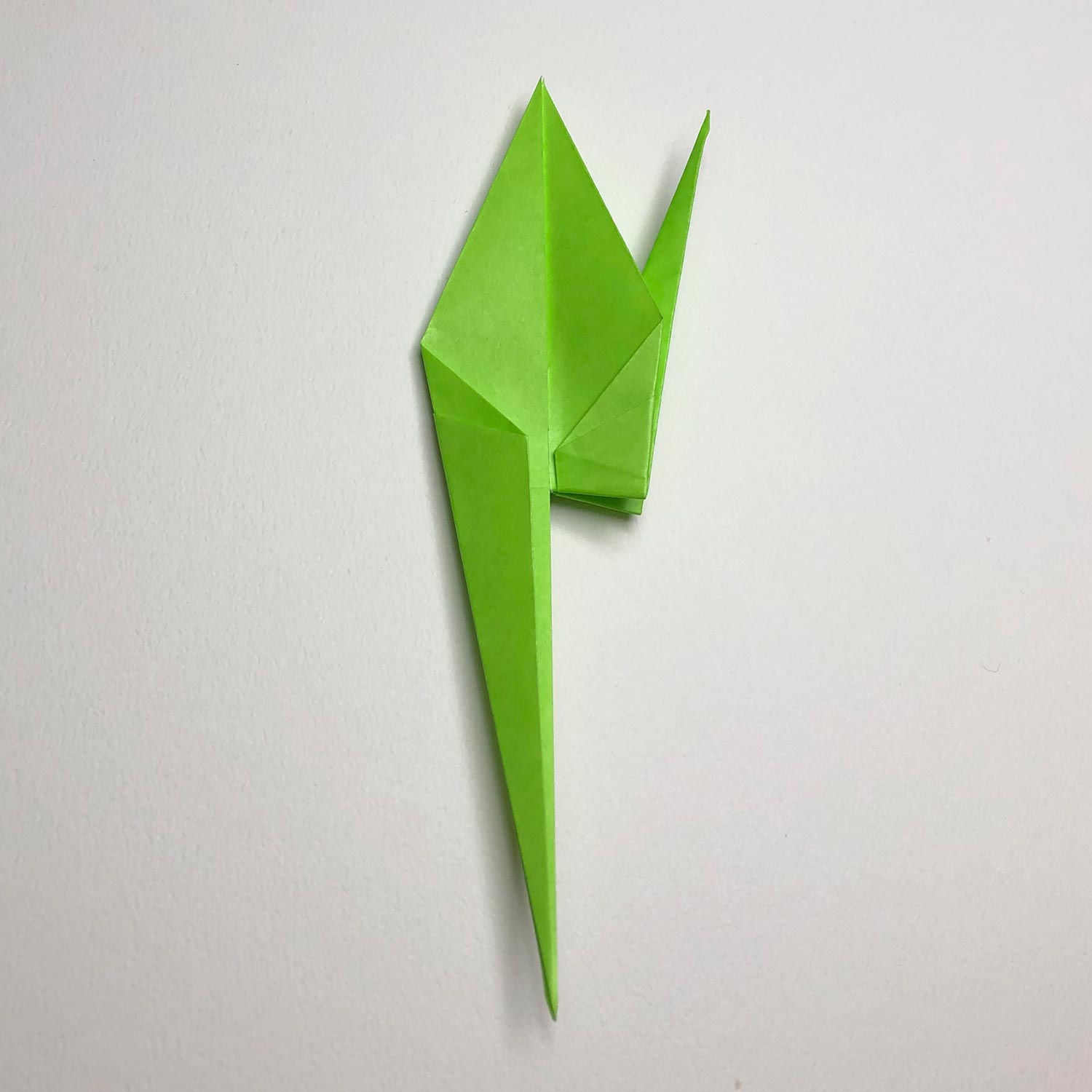
(60)
もう一方も、同じように折り目をつけましょう。

(61)
折り目をつけると、このようになります。
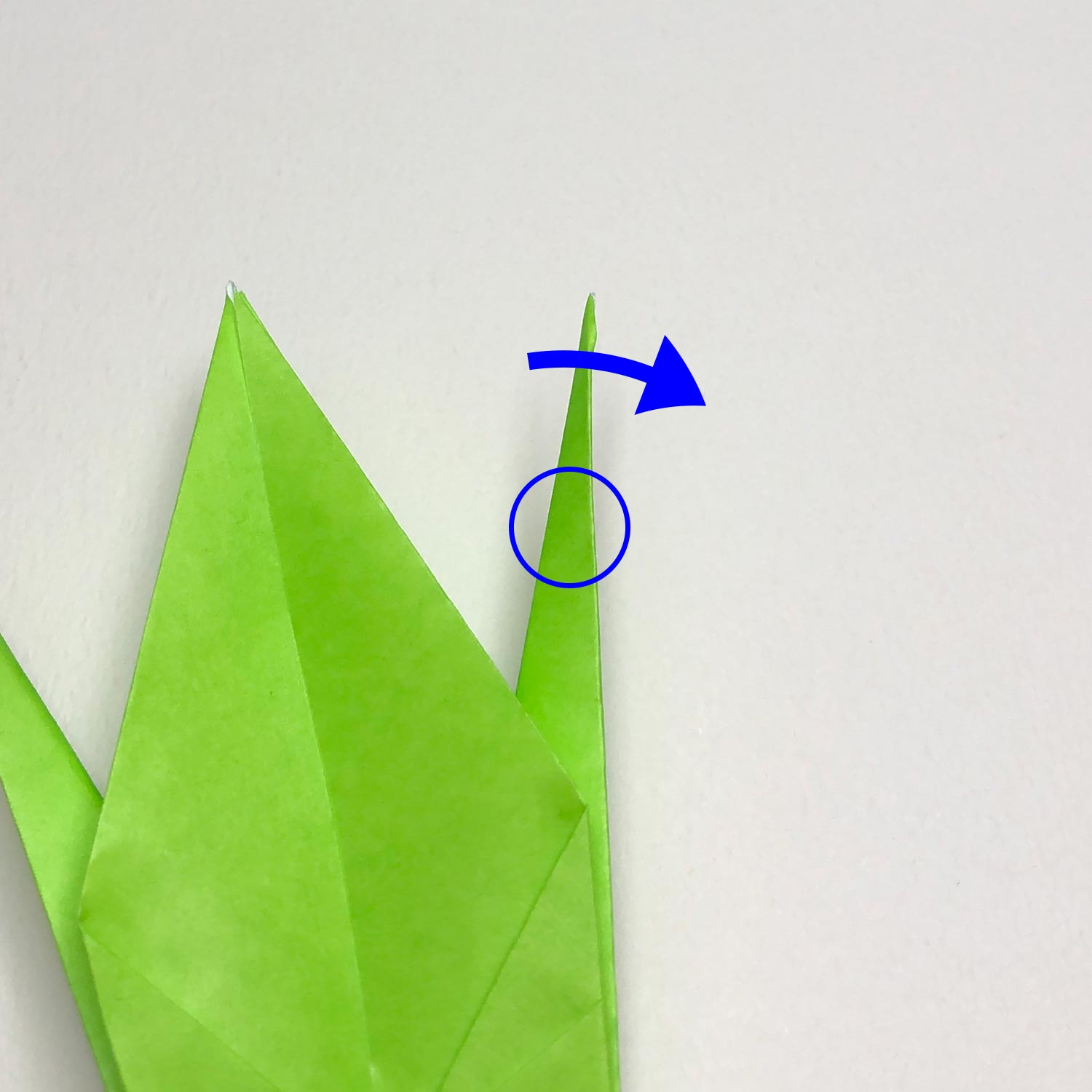
(62)
続いて、”くちばし”を折っていきましょう。
青い丸のところを、両側からつまみ、
先端を矢印の方向に動かして、軽く折り目をつけていきます。
つまむ位置(青い丸のところ)を変えると、”くちばし”の長さが変わります。

(63)
軽く折り目をつけると、このようになります。
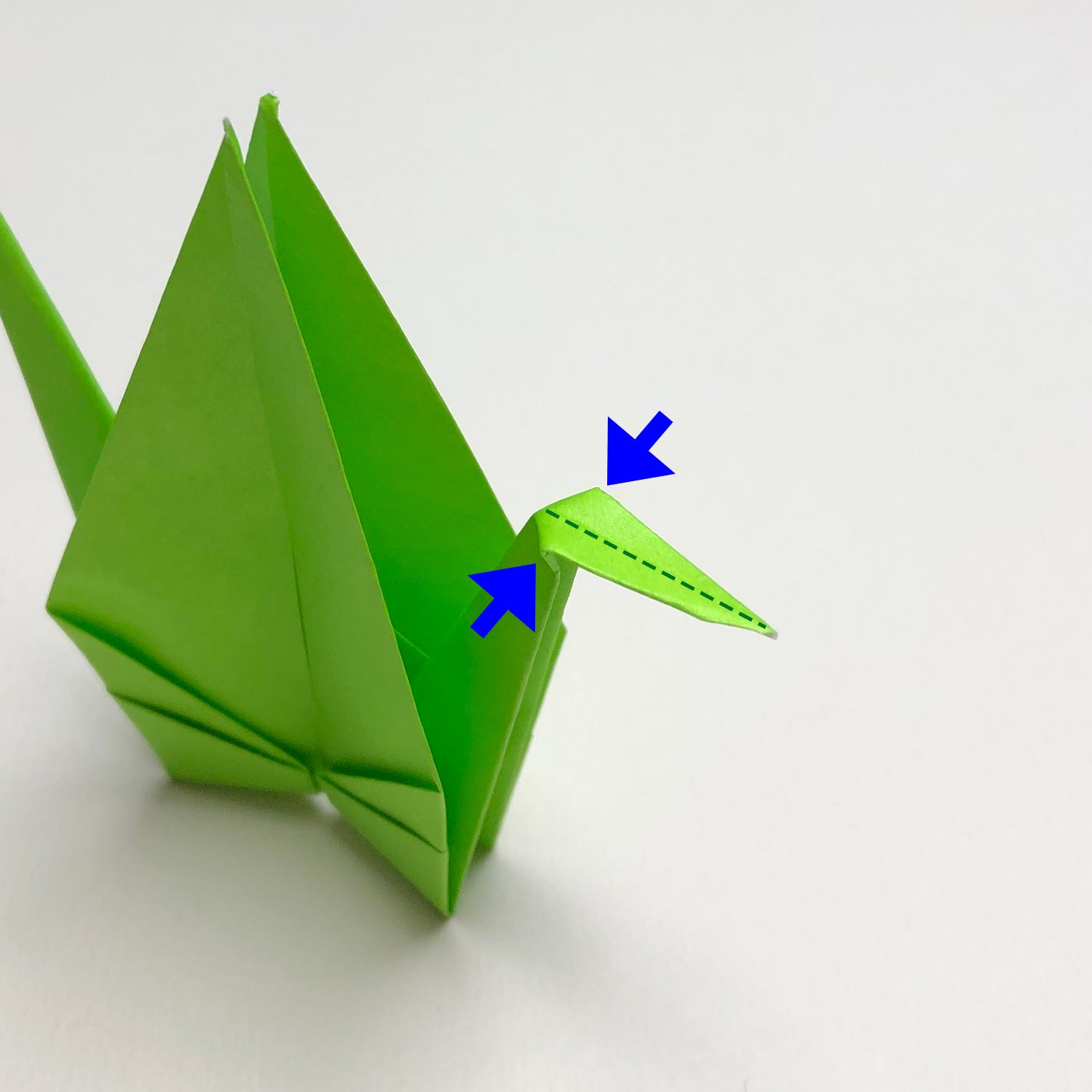
(64)
矢印のところをつまみながら、
点線部分に折り目をつけましょう。
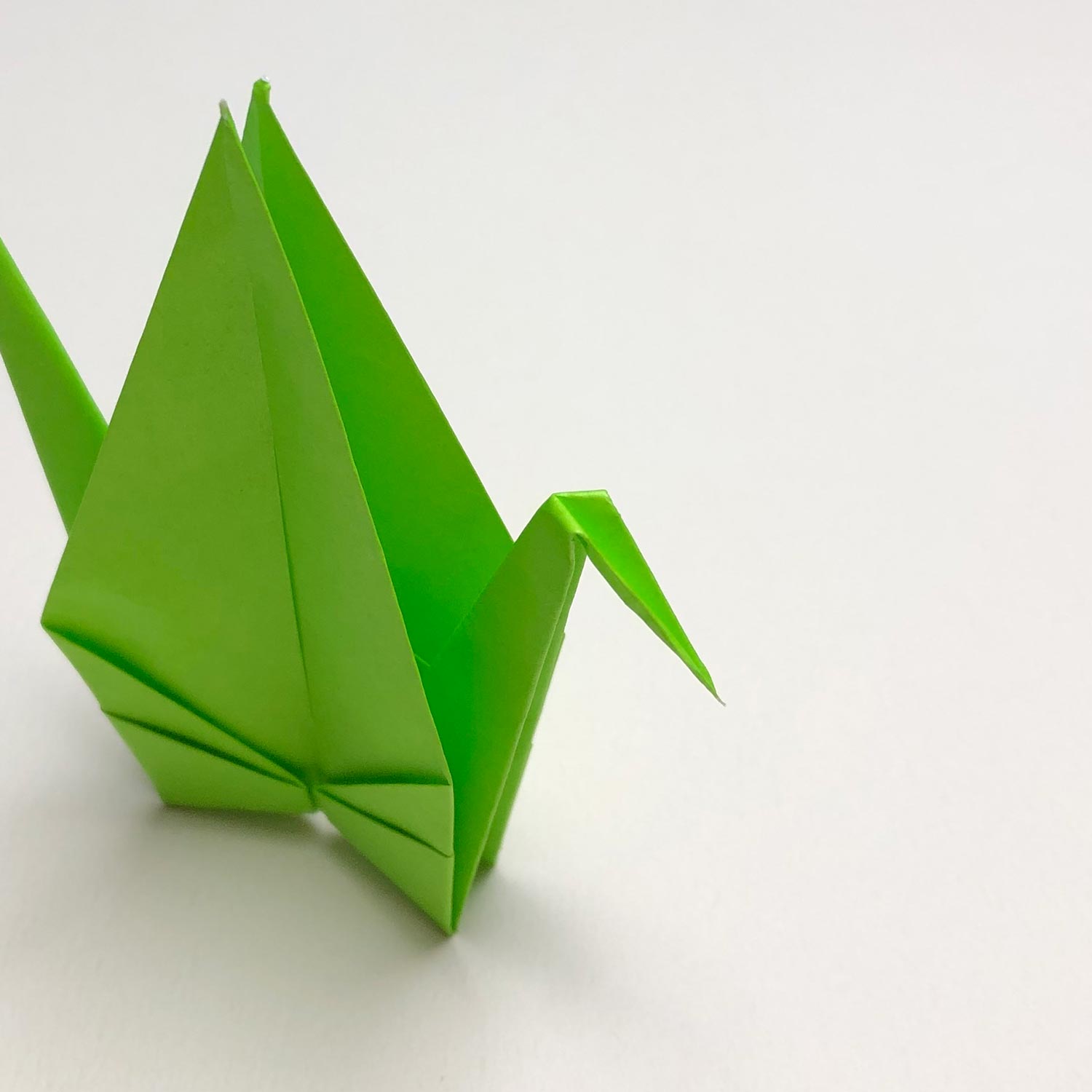
(65)
折り目をつけると、このようになります。
これで、”くちばし”を折ることが出来ました。

(66)
最後に”つばさ”を広げていきましょう。

(67)
はじめに、写真のように、少し開きます。
”つばさ”の広げ方は、2パターンあるので、
お好みのパターンで広げましょう。
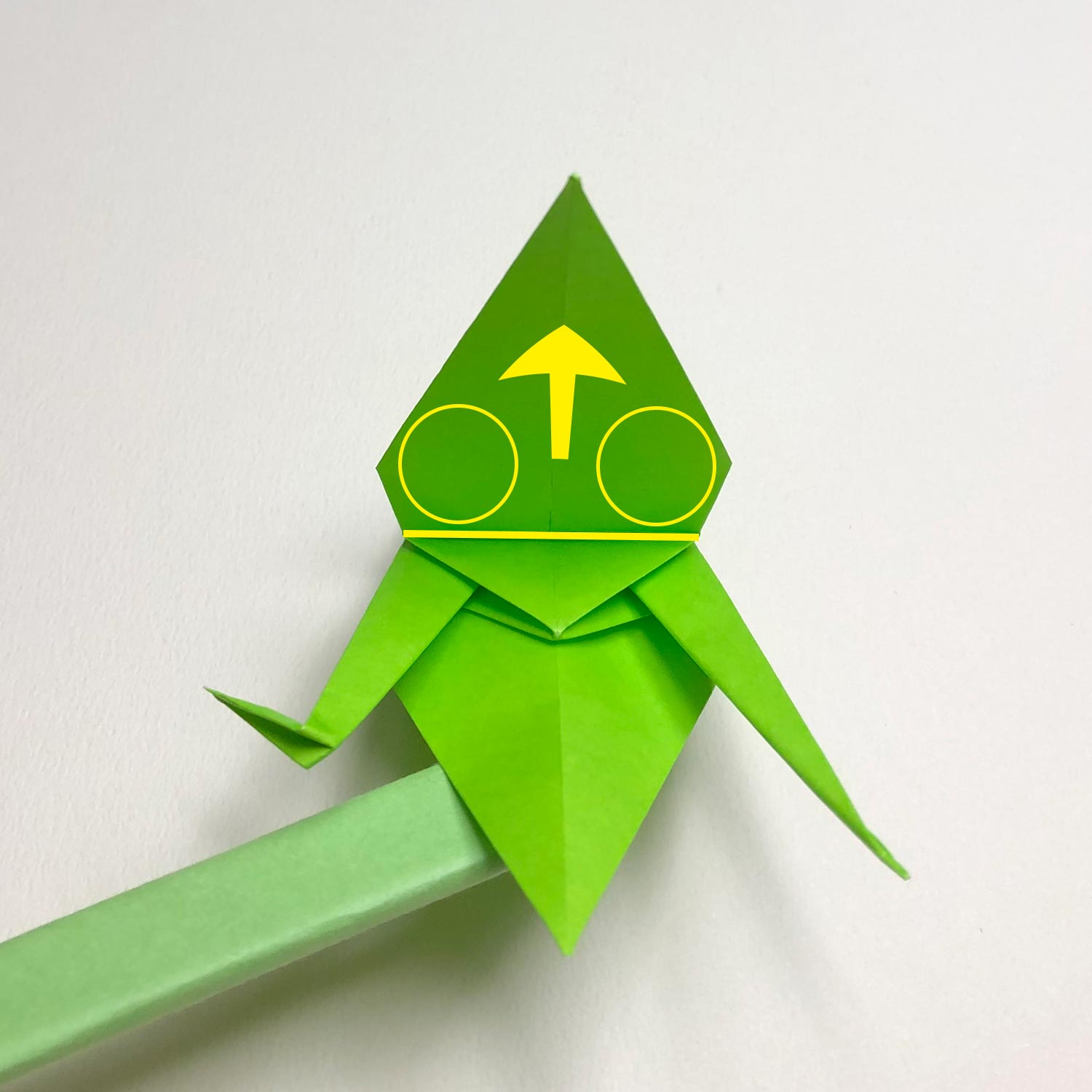
(68)
パターン1は、
”つばさ”に折り目をつける方法です。
黄色い丸のところをつまみ、黄色い線に折り目をつけるように、
矢印の方向にめくっていきます。
完全に折り目がつく”少し手前”のところまで折り目をつけると、”つばさ”が綺麗に広がります。

(69)
”つばさ”に折り目をつけると、このようになります。
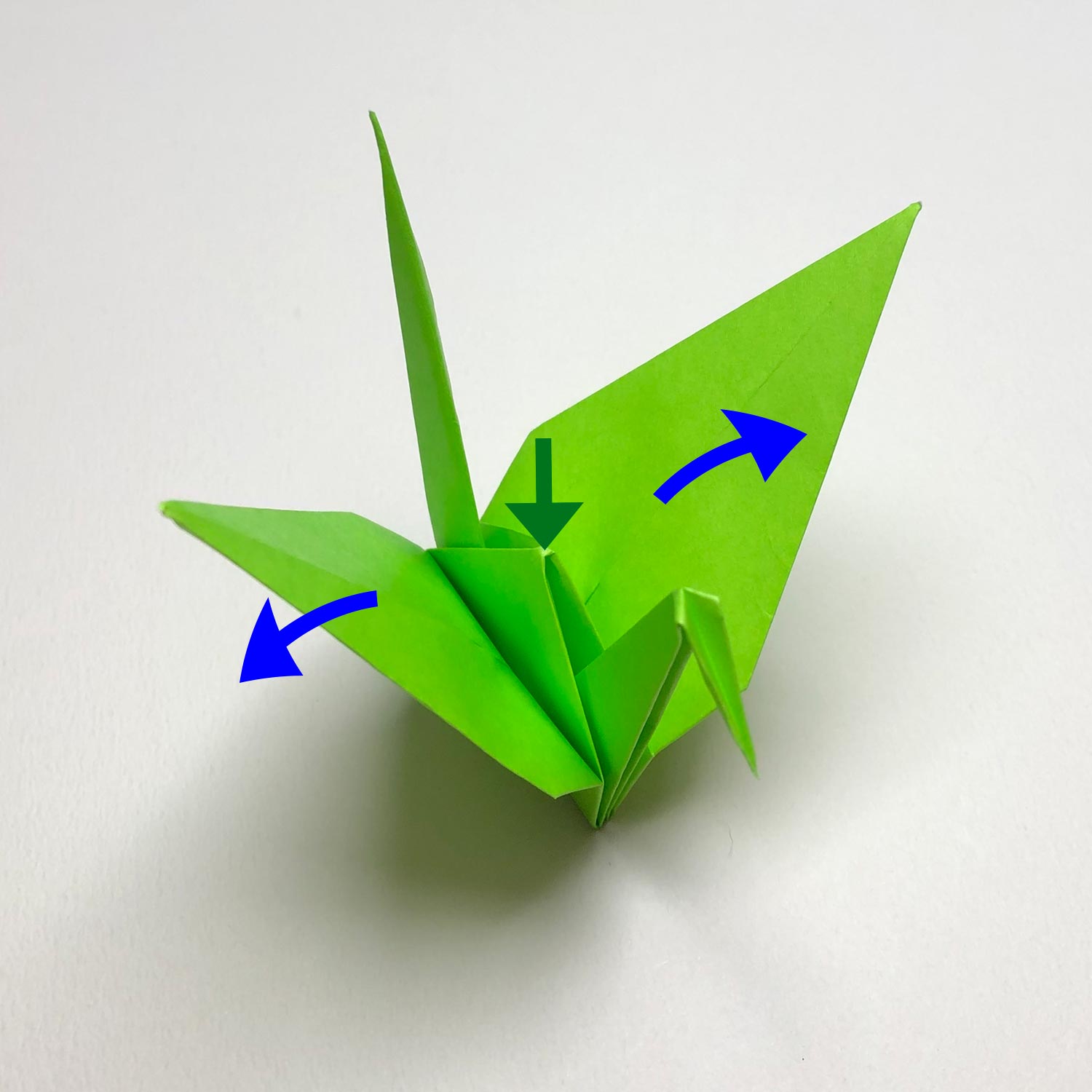
(70)
パターン2は、
”せなか”を膨らませる方法です。
両側の”つばさ”を外側に動かしながら、”せなか”の部分を上から押していきます。
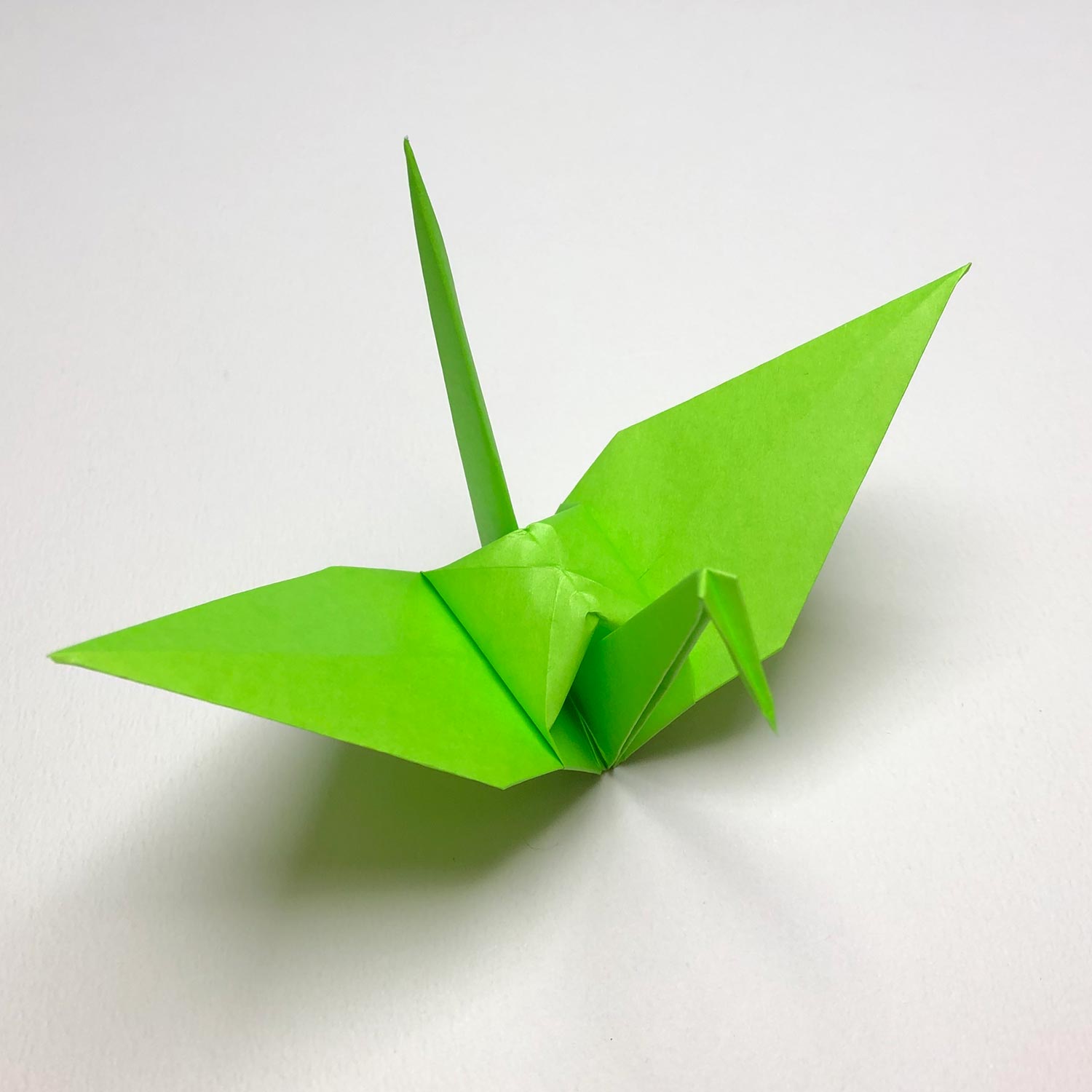
(71)
”せなか”を膨らませると、このようになります。
連鶴(れんづる)は、パターン1で”つばさ”を広げることが多いです。

折り鶴の完成です!
当サイトでは、連鶴の折り方もご紹介しております。
はじめて連鶴を折る方は、下記のページがおすすめです!

約40種類の連鶴の完成イメージは、下記のページからご覧になれます。